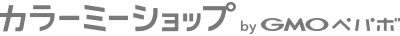ランキング
-
 【超貴重☆】世界遺産屋久島から持ち出す正式許可を得た聖なる屋久杉・飛竜勾玉さん
【超貴重☆】世界遺産屋久島から持ち出す正式許可を得た聖なる屋久杉・飛竜勾玉さん
9,700円(税込10,670円)
-
 【再登場】魔法の結晶ガネーシュヒマール水晶のシードオブライフペンダントトップさん
【再登場】魔法の結晶ガネーシュヒマール水晶のシードオブライフペンダントトップさん
26,600円(税込29,260円)
-
 広い視野や深い洞察力を与える幸運の石☆ファルコンアイ勾玉ネックレス
広い視野や深い洞察力を与える幸運の石☆ファルコンアイ勾玉ネックレス
4,800円(税込5,280円)
-
 気持ち良い癒しを届けてくれるラベンダーアメジストさざれさん 500g
気持ち良い癒しを届けてくれるラベンダーアメジストさざれさん 500g
SOLD OUT
-
 【ご祈祷石さんでパワーアップ♪】ヘマタイト龍神様立体彫りお守り ネックレスタイプと握りお守りタイプ
【ご祈祷石さんでパワーアップ♪】ヘマタイト龍神様立体彫りお守り ネックレスタイプと握りお守りタイプ
10,700円(税込11,770円)
-
 向こう側が透けるほど透明で爽やかなグリーンアメジスト プラシオライトさん
向こう側が透けるほど透明で爽やかなグリーンアメジスト プラシオライトさん
SOLD OUT
-
 【送料無料】バイオレットフローライトが花冠のようにキラキラ乗ったホワイトセレスタイトさん
【送料無料】バイオレットフローライトが花冠のようにキラキラ乗ったホワイトセレスタイトさん
23,000円(税込25,300円)
-
 ピラミッド型に美しく磨かれたお守りのネックレス・ストラップ二種類【マグネサイトさん】のページ
ピラミッド型に美しく磨かれたお守りのネックレス・ストラップ二種類【マグネサイトさん】のページ
3,500円(税込3,850円)
-
 【送料無料】神聖さが空間に広がる、アメジストのカテドラル=大聖堂のような美しい原石さんたち
【送料無料】神聖さが空間に広がる、アメジストのカテドラル=大聖堂のような美しい原石さんたち
12,000円(税込13,200円)
-
 素晴らしい水晶さんで作った大きな勾玉のネックレス
素晴らしい水晶さんで作った大きな勾玉のネックレス
SOLD OUT
-
 ポマンダー ローズピンク
ポマンダー ローズピンク
6,363円(税込6,999円)
-
 【最高の神社につながるエネルギー】伊勢巡礼と正式参拝で頂いた高波動の流れにつながるお届け福!
【最高の神社につながるエネルギー】伊勢巡礼と正式参拝で頂いた高波動の流れにつながるお届け福!
5,000円(税込5,500円)
-
 神聖な湖の小さなかけらみたいな、レイクブルーフローライトさん
神聖な湖の小さなかけらみたいな、レイクブルーフローライトさん
SOLD OUT
-
 幸せでうれしい報告や、成功・勝利・合格の知らせと仲良し、陽のエネルギーと仲良しなチェリーブロッサムアゲートのペンダントトップさん
幸せでうれしい報告や、成功・勝利・合格の知らせと仲良し、陽のエネルギーと仲良しなチェリーブロッサムアゲートのペンダントトップさん
6,800円(税込7,480円)
-
 陰と陽を上手にバランスをとっていくのに、すごく助けになってくれる二つの原石さん★ガーネットさんとパイライトさんペア
陰と陽を上手にバランスをとっていくのに、すごく助けになってくれる二つの原石さん★ガーネットさんとパイライトさんペア
5,800円(税込6,380円)
-
 私に驚きの治癒体験をさせてくださったすごいアマビエ様☆ローズクォーツさんとアマゾナイトさんの、すごい癒しのエネルギーアマビエ様ペア
私に驚きの治癒体験をさせてくださったすごいアマビエ様☆ローズクォーツさんとアマゾナイトさんの、すごい癒しのエネルギーアマビエ様ペア
4,200円(税込4,620円)
-
 魔除けと浄化のスペシャリスト☆オニキスと伊勢巡礼水晶ブレスレットさん
魔除けと浄化のスペシャリスト☆オニキスと伊勢巡礼水晶ブレスレットさん
10,000円(税込11,000円)
-
 【再登場!】三日月の満ちる力と、ラピスラズリの、最強組み合わせさん♪
【再登場!】三日月の満ちる力と、ラピスラズリの、最強組み合わせさん♪
2,900円(税込3,190円)
-
 自然と宇宙との調和、そして地球上での魂の家族との出会いと調和、ワンネスに導く、アメジストスピリットクォーツさん
自然と宇宙との調和、そして地球上での魂の家族との出会いと調和、ワンネスに導く、アメジストスピリットクォーツさん
9,000円(税込9,900円)
-
 【三個セット♪超希少☆彡】世界が驚いた採掘☆奈良天川村産 レインボーガーネットさんの原石!!
【三個セット♪超希少☆彡】世界が驚いた採掘☆奈良天川村産 レインボーガーネットさんの原石!!
3,900円(税込4,290円)
-
 伊勢神宮ご祈祷水晶さんとピンクゴールドカラーにラッピングされたヘマタイトさんのブレスレット
伊勢神宮ご祈祷水晶さんとピンクゴールドカラーにラッピングされたヘマタイトさんのブレスレット
10,000円(税込11,000円)
-
 豊かさととっても仲良しなルチルクォーツさんを、女性らしく美しく身に着けられるブレスレットさん♪
豊かさととっても仲良しなルチルクォーツさんを、女性らしく美しく身に着けられるブレスレットさん♪
10,000円(税込11,000円)
-
 【毎日受け取る】愛と感謝の未来を支える祈りヒーリング お申し込み
【毎日受け取る】愛と感謝の未来を支える祈りヒーリング お申し込み
3,000円(税込3,300円)
-
 妖精さんたちの声を聞き、アセンションを助ける トロレアイトの原石さん
妖精さんたちの声を聞き、アセンションを助ける トロレアイトの原石さん
5,800円(税込6,380円)
-
 【超貴重】願いをかなえるのが大得意な「ラッキーを生み出す大きなラピスラズリさん」を連れた、金龍神様ストラップ
【超貴重】願いをかなえるのが大得意な「ラッキーを生み出す大きなラピスラズリさん」を連れた、金龍神様ストラップ
5,800円(税込6,380円)
-
 美しい海のような、幸せいっぱい呼び込んでくれるクリソコラさんのペンダント(シルバー925ワイヤー使用)
美しい海のような、幸せいっぱい呼び込んでくれるクリソコラさんのペンダント(シルバー925ワイヤー使用)
5,700円(税込6,270円)
-
 タロットリーディング スリーカードスプレッド(掲載OKの方 2,000円の割引あり)
タロットリーディング スリーカードスプレッド(掲載OKの方 2,000円の割引あり)
5,000円(税込5,500円)
-
 タロットリーディング【ヘキサグラムスプレッド】(掲載OKの方 2,000円の割引あり)
タロットリーディング【ヘキサグラムスプレッド】(掲載OKの方 2,000円の割引あり)
8,000円(税込8,800円)
-
 【お値下げ!】宇宙から届くエネルギーとトーラスエネルギーを整える、バジュラのような両剣研磨水晶さん
【お値下げ!】宇宙から届くエネルギーとトーラスエネルギーを整える、バジュラのような両剣研磨水晶さん
7,500円(税込8,250円)
-
 ゴールデンヒーラーをもっとパワフルにしたみたいな、ゴールデンヒーロー水晶さんたち!
ゴールデンヒーラーをもっとパワフルにしたみたいな、ゴールデンヒーロー水晶さんたち!
6,800円(税込7,480円)
-
 フルオーダーメイドブレスレットさんお申し込み【セミハイクラス】
フルオーダーメイドブレスレットさんお申し込み【セミハイクラス】
11,000円(税込12,100円)
-
自動車に贈る様々な「愛と感謝の祈り」を受け取るヒーリングワーク
5,000円(税込5,500円)
-
 淡水パールが導く きらきらのさわやかブレスレットさん 三種
淡水パールが導く きらきらのさわやかブレスレットさん 三種
4,700円(税込5,170円)
-
 パワフルな【豊かさ・金運財運を届けてくれる「三種の神石さん」】セット
パワフルな【豊かさ・金運財運を届けてくれる「三種の神石さん」】セット
6,000円(税込6,600円)
-
 クイントエッセンス セラピスベイ
クイントエッセンス セラピスベイ
6,363円(税込6,999円)
-
 ヒーリング・クリスタル・ブレス ハイクラス
ヒーリング・クリスタル・ブレス ハイクラス
11,000円(税込12,100円)
-
 【送料無料】伊勢神宮ご祈祷水晶さん☆最高な状態の水晶さんで作るブレスレットさん お届けいたします!!
【送料無料】伊勢神宮ご祈祷水晶さん☆最高な状態の水晶さんで作るブレスレットさん お届けいたします!!
12,000円(税込13,200円)
-
 【送料無料】LOVEセット二種類(恋愛バージョン・新しい家族お迎えバージョンあります)
【送料無料】LOVEセット二種類(恋愛バージョン・新しい家族お迎えバージョンあります)
29,000円(税込31,900円)
-
空間や物の浄化・癒しに☆乾燥ホワイトセージ
2,900円(税込3,190円)
-
 パワフルな【癒しと健やかさを届けてくれる「三種の神石さん」】セット!!
パワフルな【癒しと健やかさを届けてくれる「三種の神石さん」】セット!!
6,000円(税込6,600円)
-
 【最高級を再入荷♪】超貴重になってきています☆はちみつオレンジカルサイトさんのスフィア&ハート
【最高級を再入荷♪】超貴重になってきています☆はちみつオレンジカルサイトさんのスフィア&ハート
12,000円(税込13,200円)
-
 ねこちゃんの形のローズクォーツで出来た平たいワンド(魔法の杖!)☆ねこねこローズクォーツさん
ねこちゃんの形のローズクォーツで出来た平たいワンド(魔法の杖!)☆ねこねこローズクォーツさん
4,800円(税込5,280円)
-
 【超貴重】願いをかなえるのが大得意な「ラッキーを生み出す大きなラピスラズリさん」を連れた、銀龍神様ストラップ
【超貴重】願いをかなえるのが大得意な「ラッキーを生み出す大きなラピスラズリさん」を連れた、銀龍神様ストラップ
5,800円(税込6,380円)
-
 古代の叡智、神聖なる波動を秘めたエナジーカードさん♪
古代の叡智、神聖なる波動を秘めたエナジーカードさん♪
3,400円(税込3,740円)
-
 集中力・行動力を高める スタイリッシュヘマタイトブレスレットさん
集中力・行動力を高める スタイリッシュヘマタイトブレスレットさん
2,800円(税込3,080円)
-
 フルオーダーメイドブレスレットさんお申し込み【スタンダードクラス】
フルオーダーメイドブレスレットさんお申し込み【スタンダードクラス】
8,600円(税込9,460円)
-
 通帳さんの守り人・セイントタイガーアイ・ルースさん 2個セット
通帳さんの守り人・セイントタイガーアイ・ルースさん 2個セット
3,300円(税込3,630円)
-
 ペンデュラム ローズクォーツ キラキラのダウジング(オーダーメイド)
ペンデュラム ローズクォーツ キラキラのダウジング(オーダーメイド)
4,900円(税込5,390円)
-
浄化と、清い空間を作る水晶さざれさん500g 中・特大あります
5,100円(税込5,610円)
-
 水の精霊ピアス&イヤリング アクアマリンとムーンストーン(silver925ピアス可)
水の精霊ピアス&イヤリング アクアマリンとムーンストーン(silver925ピアス可)
5,200円(税込5,720円)
-
 ヒーリングスター・シリウスアメジストさんのペンダントトップ
ヒーリングスター・シリウスアメジストさんのペンダントトップ
3,500円(税込3,850円)
-
 【送料無料】【スペシャルメンバー】『ヴィジョンクォーツ』と呼ばれるマスタークリスタルを超えるクラスの水晶さん
【送料無料】【スペシャルメンバー】『ヴィジョンクォーツ』と呼ばれるマスタークリスタルを超えるクラスの水晶さん
12,900円(税込14,190円)
-
持つ人を癒すパームストーンの形をしたネックレス・ストラップさん二種類【グリーンクォーツァイト】のページ
3,500円(税込3,850円)
-
 キラキラの幸せがいっぱい詰まったラッキーベアの水晶さん!!
キラキラの幸せがいっぱい詰まったラッキーベアの水晶さん!!
SOLD OUT
-
 とってもすてきなルチルクオーツのペンダントトップさん♪ (バチカンシルバー925)
とってもすてきなルチルクオーツのペンダントトップさん♪ (バチカンシルバー925)
5,800円(税込6,380円)
-
 深い癒しの蒼の優しさとラッキーをあなたに ラピスラズリ原石さん 原石のままorワイヤーアレンジペンダントトップ
深い癒しの蒼の優しさとラッキーをあなたに ラピスラズリ原石さん 原石のままorワイヤーアレンジペンダントトップ
6,600円(税込7,260円)
-
 パワフルな魔よけのお守り★ヘマタイト龍神様立体彫りお守り(カラフルタイプ)
パワフルな魔よけのお守り★ヘマタイト龍神様立体彫りお守り(カラフルタイプ)
10,700円(税込11,770円)
-
 穏やかでキラキラしたラベンダーアメジストのペンダントトップさん
穏やかでキラキラしたラベンダーアメジストのペンダントトップさん
3,000円(税込3,300円)
コンテンツを読む
- オーラソーマ イクイリブリアムボトルさん(50ml)の使い方
- 【ダブルターミネーティッドさんとは】
- 【レムリアンシードクリスタル とは】
- ピュアストーンサンタさんについて(現在、ストーンサンタさん受付はストップしております)
- ☆必ずお読みください☆
- ☆私たちからの大切なメッセージ(必ずお読みください)
- 【ぽいき堂プレミアムサイト(会員制・無料)】ご登録ご希望の方へ☆彡
- 【クレジットカード決済】に関する、購入者さまからのよくあるご質問
- オーダーメイドお品物のご説明・サイズの測り方・お願いごとの込め方等
- お友達紹介ポイントプレゼントについて♪
- ☆お祈り・ヒーリング等について、必ずご確認ください
- ☆ぽいき堂お品物のご感想ページ♪一覧
- ☆お客様からのご質問【Q&A】一覧ページ♪
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
モバイルショップ

☆Mさまよりご質問
・同じ神様をまつる神社が全国にありますが、何か違いとかってあるのでしょうか?
猿田彦神社が○○県内(←Mさんのお住まいの地域)にあるのは知ってましたが、さっき調べたら天照大神の神社もありました。
神社の大きさ?の違いとかでしょうか?
☆お答え♪
神社っていうのは、すごく古いものは、当時のシャーマン的な「巫女さん」たちが、神様のエネルギーをキャッチしやすい場所、「パワースポット」のすごく強力な場所を、歩いて探したり、その場に直感で「呼ばれたり」、神様ご自身からの「ここに神社を作りなさい」というメッセージを受け取ったりして、作られていきました。
例としては、歩いて探したバージョンは、伊勢神宮。
「元伊勢」という、伊勢神宮の候補となった場所が、今もたくさん残っています。そこも、候補になったくらいなので、すごくパワフルな場所です。
ほかにもいろんなバージョンがあるかもしれませんが、まずそうして「おおもと」となる神社が作られます。
そして、でもそれ以外の場所にも、同じ名前の神社が全国にあるのは、「勧請」といって、おおもとの神様の「魂・霊」を、ちょっと分けてもらって、地方にもっていって祀る、ということが、長い歴史の中でたくさん行われたからです。
※勧請という言葉は、もともとは仏教用語らしいのですが、神仏習合ということが行われて以降、神社を分ける場合も「勧請」というようです。
で、そうやって例えば、長野県に諏訪大社という大きな神社がありますが、その諏訪大社の「分霊(わけみたま・ぶんれい)」をもらってきて、地方に小さな「諏訪神社」を作ったりします。
じゃあ、どうして小さな神社を作ったのかというと、昔、身分の高い武士や、とても裕福な商人が、いわゆる転勤や、店舗を増やすなどで引越しをすることがありました。
その際、ずっと先祖代々守っていただいていた地元の神様の神社に、もう引越しをしたらお参りできなくなる可能性がありました。
というのは、昔はほぼ徒歩での移動なので、大阪東京間でも、ゆっくり移動したら一か月くらいかかったんですね。
徒歩で一日平均30km歩く!それで大体15日くらいかかる。
でもそんなに早く歩けるのは、健康で鍛えている人たちなので、お年寄りとか、女性・子供だったら、その倍くらいはかかる。
また、時期によっては「移動するための旅行証明書」みたいなものが必要で、それを申請して取得するのにも、結構厳しかったんです。
さらに昔の人は短命でした。60歳まで生きたらすごい!ってことで、赤いちゃんちゃんこを着てお祝いしたんですね。
だから、そういうことをいろいろ加味すると、もう元住んでいたところには、簡単に戻ってこれないかも、ということは結構リアルな感覚だったそうです。
それで、それじゃあ引越し先に、自分の崇敬している神社の「分霊」をいただいていって、新しく小さな神社を作って、そこにお祀りましょう、ということが、たくさんあったのだそうです。
ほかには、その地域の主である武将とか、リーダー的存在の人が「○○の神様に助けられた」という体験をして、そのお礼の気持ちを込めて、「○○の神様」を祀っている神社に行って「分霊」をいただいてきて…というパターンもあるようです。
すると、地方にあちこち、小さい「諏訪神社」とか「春日神社」とか「白山神社」ができてくるわけです。
あとは「八幡」って付く神社がたくさんあると思います。
この「八幡」という神社は、都や武士の守護神、という感じの神様として、すごくあちこちに作られた歴史があるんです。
例えば平安京の鬼門封じとして、平安京の北東方角=鬼門に、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)が作られたりしました。
また、武将の人たちは必勝の神様として、自分の領土のあちこちに作っていったそうです。
有名なのは、源頼朝さん。
この方は、さっき書いた石清水八幡宮から「分霊」していただいて、鎌倉に鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)を作ったんです。
そしたら、その部下の人たちがみんな「えー、それいいなあ!私の家の近くにも、必勝の神様来てほしい!!」ってなって、それぞれの地元に、どんどん「八幡神社」を作っていったんだそうです。
そしてさらに「お前は今度転勤して、あっちの地域を守りに行ってくれ」と、引越しになったら、そこでもまた八幡神社を作る、ということをどんどんやっていて、気が付いたら日本中に、次々に八幡さまができて、今でも約7800社あるそうです。
ちなみに「八幡」と付く神社は、厄除け災難除け、商売繁盛、必勝合格、安産などなど、いろんなことでお守りくださる、とってもありがたい神社です。
神様としては「私たちのご先祖である、昔むかしの神様レベルの天皇様をお祀りしている」ので、私たちの超ご先祖様。
だから、その神様から見たら私たち子孫は、「ひひひひひひひひひ…孫」みたいな存在であり、かわいくてすごく大切に守ってくださっている状態です。
そんな八幡様を、みんなで増やしていって、日本中にいてくださるようにしていったということです。
みんな神様大好きなんですね(^^*
自分の地域の神社があって、そこを守ってもらえたら安心ですもんね。
そして、そうした同じ名前の大きな神社と小さな神社の違いですが、
一応、大きなおおもとの神社は、やはり「分霊(わけみたま・ぶんれい)」ではなくて「親御霊(おやみたま)」なので、一番おおもとの神社にお参りされるのがおすすめですが、だからと言って、小さい神社だから功徳が薄いとか、パワーが弱いとか、そういうことではありません。
地方の小さい神社でも、心を込めてお参りされれば、ちゃんと「テレビ電話」というか、今でいうと「zoom」みたいな「LINE電話」みたいなものが神様とつながっているので、直接お会いできなくてもちゃんと伝わります。
ただ、神社って本来は、お願い事をしに行くところ、ではなく、私たちが神様に「いつも24時間、陰日なた無く守ってくださってありがとうございます」と、お礼を伝える場所、感謝をお届けする場所として、神様に降りてきていただく場所です。
なので、そう考えると、大切な人にお礼を伝える場合は、やっぱりいつかはおおもとの神社へ行って…というのが、礼儀としておすすめですよ、ということになるんだと思います。
すごくお世話になっている方や、ご自分のおじいさんおばあさんに、なかなか会いに行くことができなくても、お電話でお話しするだけでもすごく喜んでもらえることって、ありますよね。
でも、やっぱり時々は直接会いに行くことで、さらに喜んでいただける、みたいな感じです。
そういうわけで、長くなりましたが、あちこちに同じ名前の神社があるのは、こうしたいきさつで増えていったためです。
そして、大小の違いは、おおもとの神社か、分霊をもらってきた神社か、ということになります!!
(^^*
Mさん、素敵なご質問をいただき、ありがとうございました!!
☆.。.:*☆.。.:*☆.。.:*☆.。.:*☆.。.:*